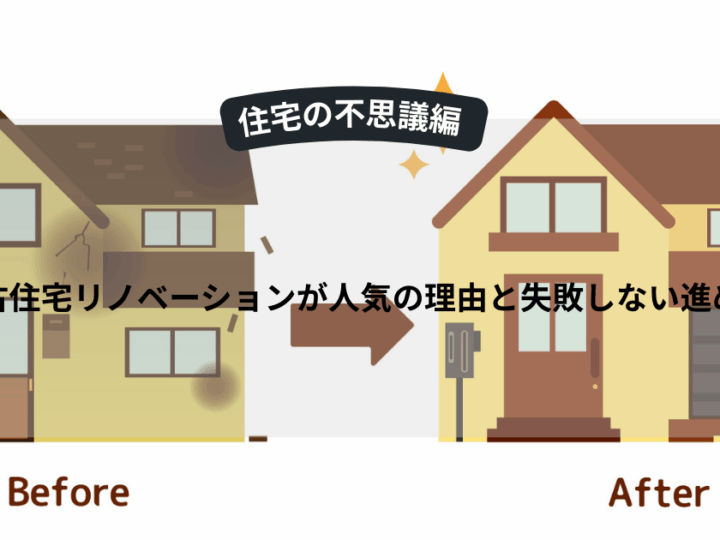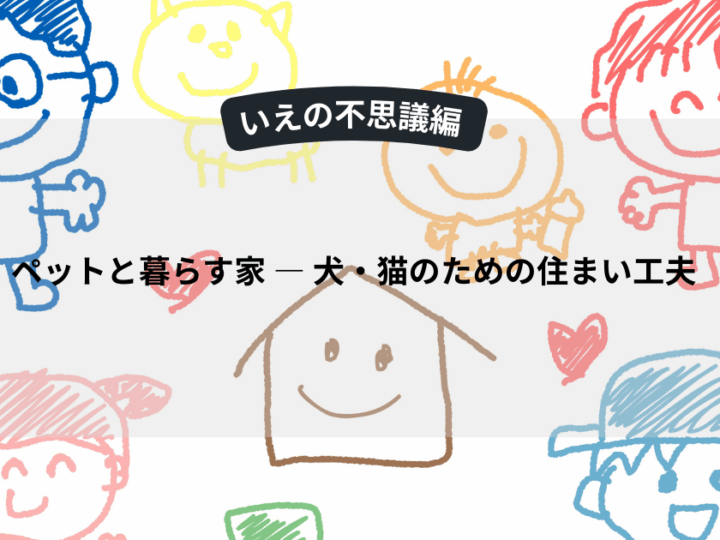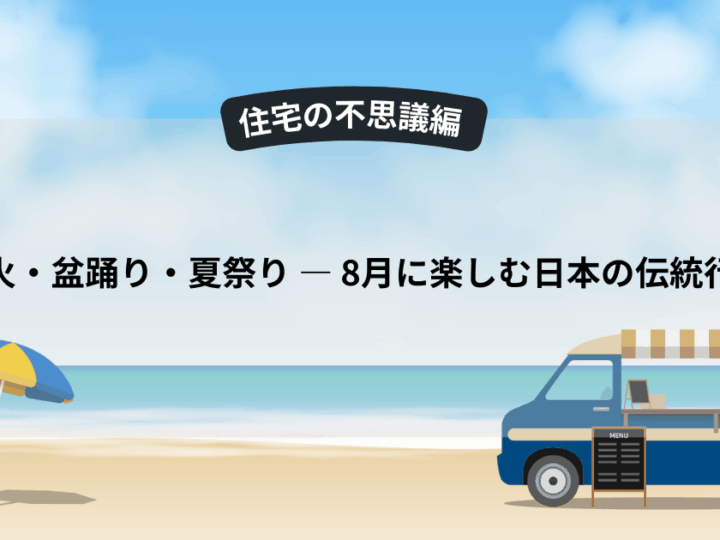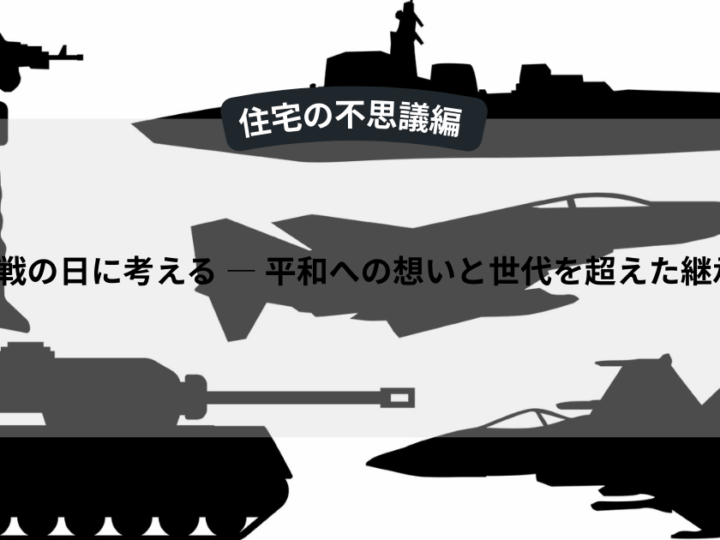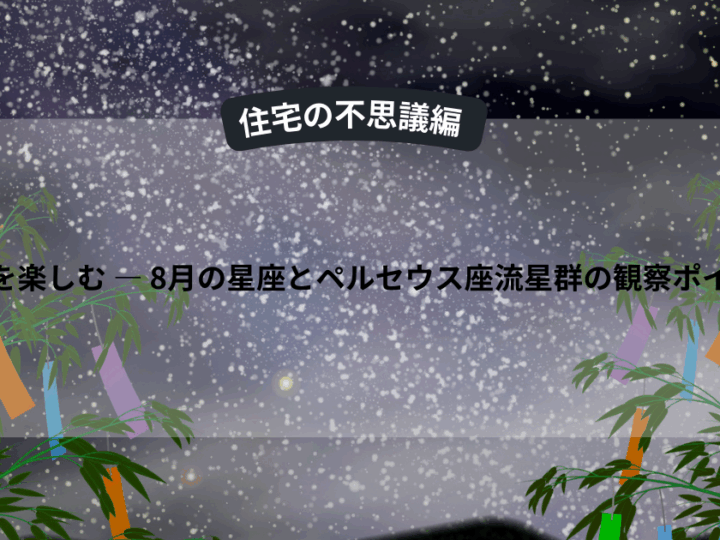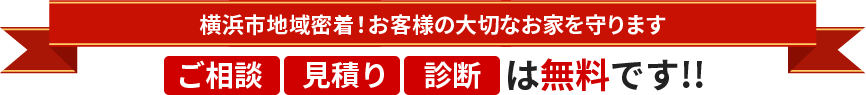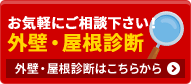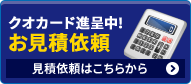中古住宅と新築、どちらが本当にお得?費用と価値を徹底比較
皆様こんにちは! 横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。 横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪ まず、 家を購入するとなると、多くの人が「新築か中古か」で迷いますよね。でもやはり新築の方が人気ではありそうですね。 私自身も住宅購入について考えたとき、「ピカピカの新築は魅力的だけど、予算を考えると中古も気になる」という気持ちになりました。 特に、横浜は物件価格がかなり高い方ではありますし中古住宅も立地が良くとても魅力的でした。 実際のところ、価格や価値、住み心地までトータルで見たときに、どちらが本当にお得なのでしょうか。 新築住宅の特徴とメリット 新築住宅の最大の魅力は「誰も住んでいない新しい家に入居できる」という安心感です。設備も最新で、耐震性や断熱性能も現行基準に合っています。 最新設備が使える:省エネ性能が高く、光熱費が抑えられる。耐震性も優れていて安心して住める。 メンテナンスが当面不要:10年程度は大きな修繕の心配が少ない。 資産価値の安定:新築ブランドで売却時の買い手が見つかりやすい。 間取りやデザインを自由設計できる(注文住宅の場合) 一方でデメリットもあります。 価格が高い:土地と建物を合わせると、都市部では数千万円単位の負担。 資産価値の下落が大きい:新築時点がピークで、購入直後に2割ほど下がるケースも。 立地の選択肢が少ない:便利なエリアは土地がすでに埋まっており、郊外が中心。 新築のメリット・デメリットは?中古住宅との比較や買うべき人の特徴を紹介 | お役立ち情報|一建設のリーブルガーデン 中古住宅の特徴とメリット 中古住宅の魅力は「価格の手ごろさ」と「立地条件の良さ」です。 購入費用が抑えられる:新築より2〜3割安いことが多い。 人気エリアでも選択肢がある:駅近や都心に物件が残っている。 リノベーションで自分好みにできる:古い家を現代的に改修できる。 資産価値の下落が少ない:築20年を超えると価格が安定する傾向がある。 ただし注意点もあります。 修繕費がかかる:水回りや配管、屋根などに追加費用が必要。 性能が劣る場合がある:耐震・断熱が現代基準に届いていない物件も多い。 住宅ローンの条件が厳しい場合がある:築年数によっては借入年数が制限される。 中古住宅のローン審査は厳しい?築年数による住宅ローン控除、リフォーム費込みや頭金なしローンについて | 中古マンション・戸建てリノベーション&リフォーム 費用比較:新築と中古+リノベーション ここで具体的な費用感をシミュレーションしてみます。 新築の場合 都市部の一戸建て:土地3,000万円+建物2,500万円=合計5,500万円前後。 35年ローンを組めば、月々15万円ほどの返済になるケースもあります。 中古+リノベーションの場合 中古住宅購入2,500万円+リノベーション1,000万円=合計3,500万円前後。 ローン返済は月々10万円程度に抑えられる可能性があります。 もちろん場所や規模によって差はありますが、総額で1,500〜2,000万円の差が出ることも珍しくありません。 実際には、中古住宅では購入後に修理が必要になった人も少なくありません。 新築と中古住宅どっちが得?|費用・後悔しない選び方を徹底比較【2025年版】 資産価値の違い 不動産は「建物」ではなく「土地」に価値が残ると言われます。新築住宅は購入直後の下落幅が大きい一方、中古住宅は価格がある程度落ち着いているため、資産価値が安定しています。 新築:築10年で資産価値が半分近くになることもある。 中古:築20〜30年を超えると、ほぼ土地代に近い価格で安定。 つまり「将来的に売却することを考えるなら立地重視」であり、新築・中古の差よりも場所の条件が大きく影響します。 大体の物件は土地だけの価格になる気がしますので新築だと色々な利益がのっていてとても高額になっていますね、、、 資産とは?財産や貯金との違いは?【簡単に解説】資産に入るもの一覧も紹介 | 女性副業比較ナビ(女性のための副業コラムサイト) 失敗しない選び方 新築を選ぶべき人 長期的に安心して暮らしたい人 最新の省エネ・耐震性能を重視する人 自分の希望をゼロから形にしたい人 中古を選ぶべき人 予算を抑えつつ立地にこだわりたい人 自分好みにリノベーションしたい人 売却より「住み続ける」目的を優先する人 2025年4月、建築基準法改正! 省エネ基準強化に向けて気になるポイントを徹底解説 | 仲介手数料無料のREDS 私の感想 私自身は、「コストを抑えて自分オリジナル使用にしたい人は中古住宅、誰も住んだことのない所に住みたいひとは新築」と感じました。 実際、便利な場所で新築を買うのは非常に難しいですが、中古ならまだ選択肢があります。そのうえでリノベーションすれば、思い出の詰まったオリジナルの住まいが完成するのも魅力的です。 一方で、新築の「ピカピカの家に住む喜び」はやはり特別なものがあります。長く住む家だからこそ、多少の費用差以上に「納得できるかどうか」が大切だと感じます。 お家探しはとても体力を使いますが、この家と決まれば意外とすんなり進みますね♪ まとめ 新築は安心感・最新性能・ブランド価値が強みだが、価格と資産価値の下落が課題。 中古は価格が安く立地条件が良いが、修繕や性能面のリスクを考える必要がある。 どちらが「お得」かは、家族のライフスタイルと価値観によって変わる。 住宅購入は「一生に一度の買い物」と言われますが、実際には「どんな暮らしをしたいか」を軸に選ぶのが一番の正解ではないでしょうか。お金だけでなく、家族の幸せや安心を考えたときに、自分にとっての「お得」が見えてくるのだと思います。 2025年08月29日 更新スタッフブログ


 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求