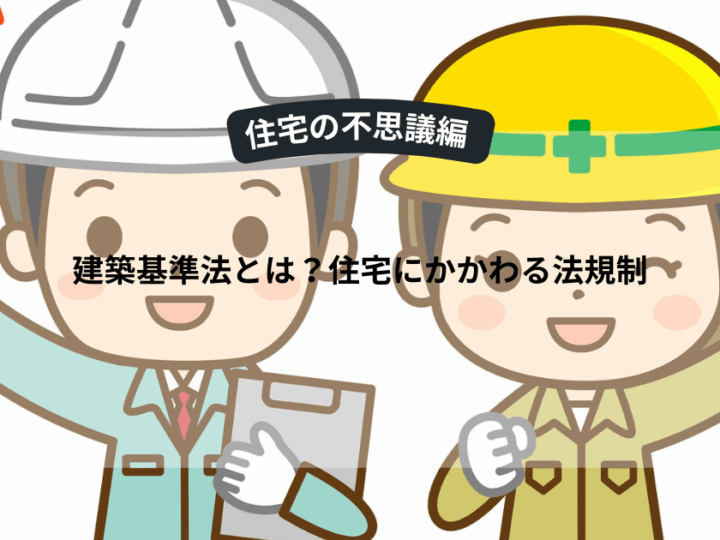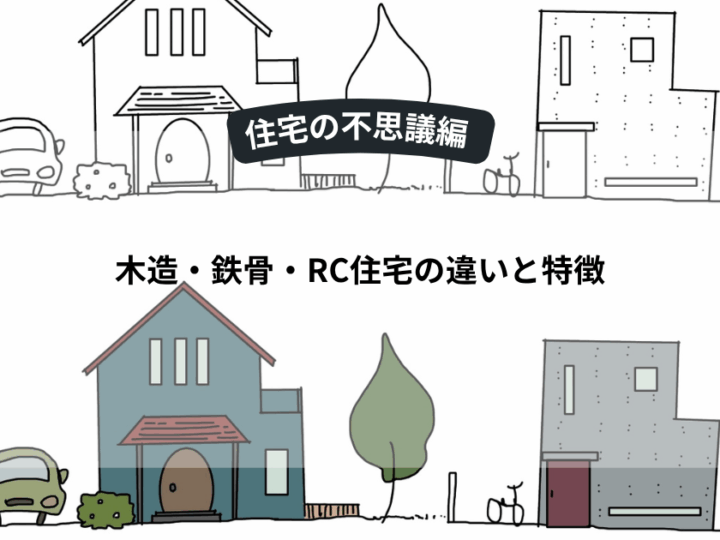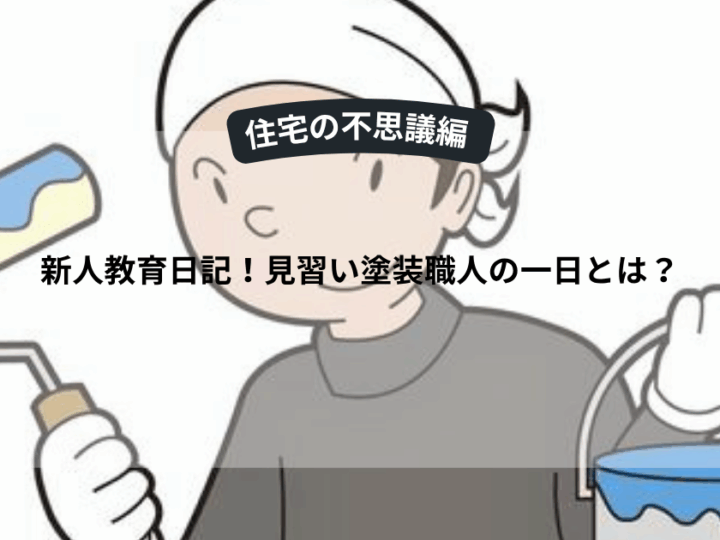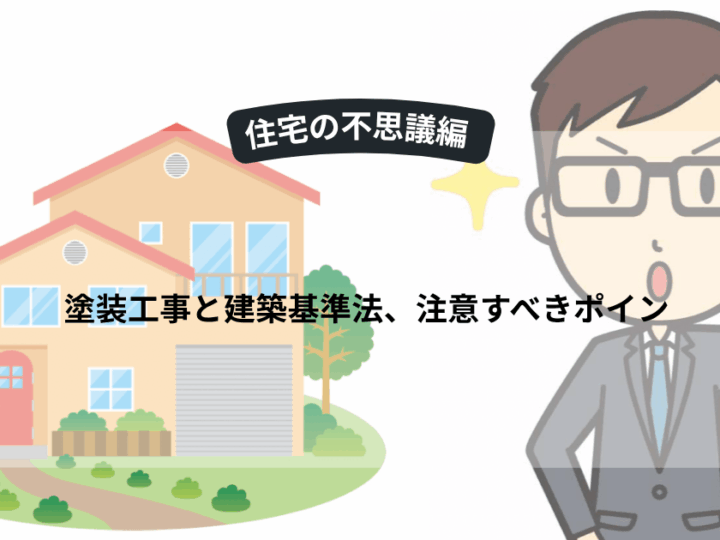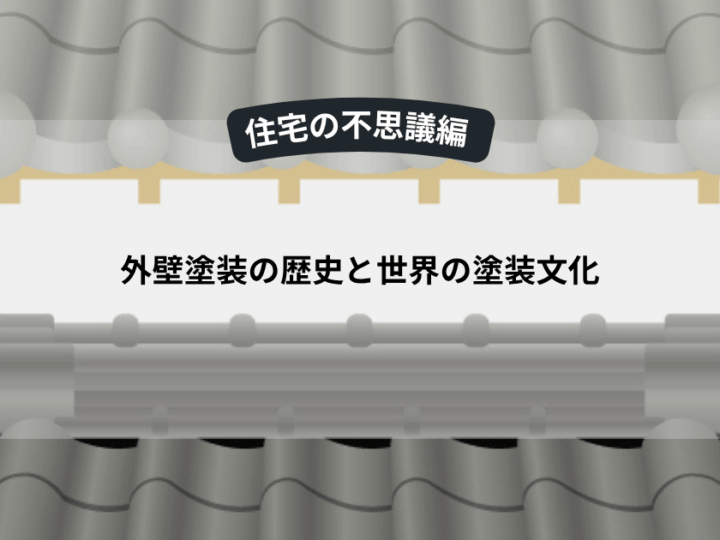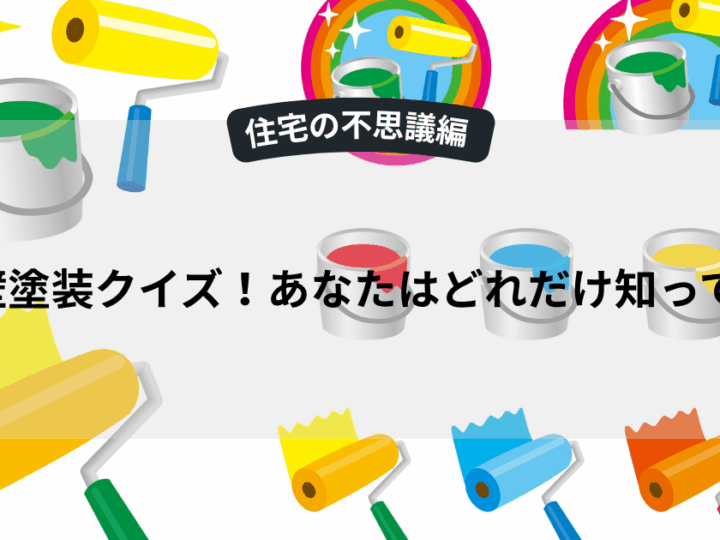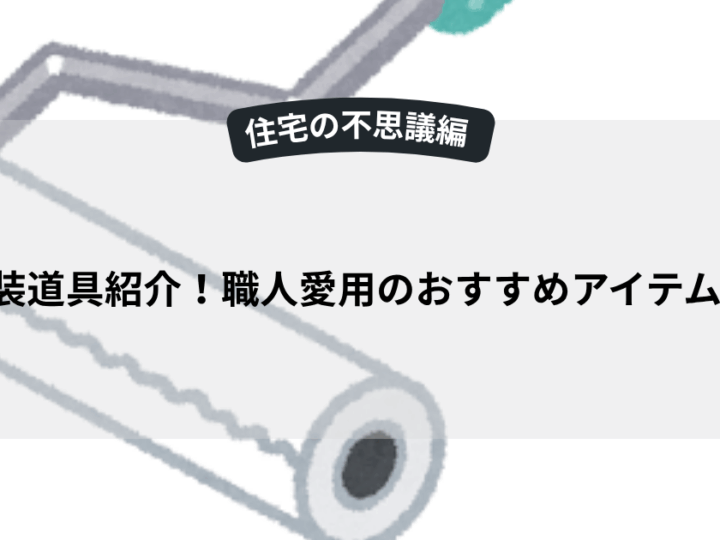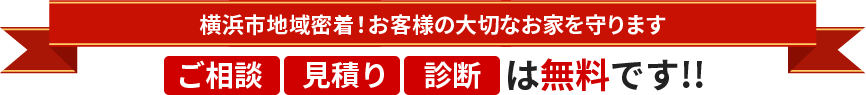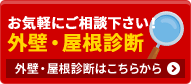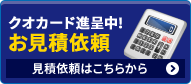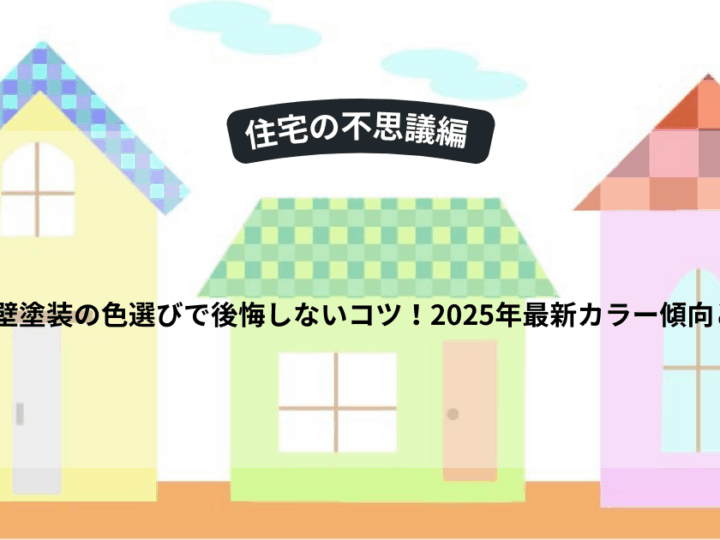
外壁塗装の色選びで後悔しないコツ!2025年最新カラー傾向とは
皆様こんにちは! 横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。 横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪ 今回は、外壁塗装での色選びについてとても重要ですので解説させて頂きます。 ぜひ、最後まで見て頂ければ嬉しいです! はじめに 外壁塗装は、家の印象を大きく左右する大切な工事です。その中でも「色選び」は、最も悩むポイントのひとつではないでしょうか。完成後に「思っていた色と違う…」「周囲から浮いてしまった…」と後悔するケースも少なくありません。そこで本記事では、外壁塗装の色選びで後悔しないためのコツと、2025年の最新トレンドカラーをご紹介します。 1. 外壁塗装で色選びが重要な理由 まず、なぜ色選びがこれほど重要なのでしょうか。 ① 外観イメージの8割は「色」で決まる 外壁は家全体の大部分を占めているため、その色味は家の印象を決定づける大きな要素です。和風・洋風・モダンなど、建物の雰囲気も色次第で大きく変わります。 ② 周囲との調和も重要 近隣の家と調和の取れていない派手な色にすると、トラブルの原因になる場合もあります。景観や街並みの美観を損なわない選択が求められます。 ③ 塗り直しは簡単ではない 外壁塗装は一度塗ると10〜15年はそのままの状態が続きます。すぐに塗り替えられるわけではないため、後悔はできるだけ避けたいものです。 色彩図鑑(色の名前と色見本一覧) | 日本と世界の伝統色 2. 後悔しないための色選びのコツ ① 「色見本」は必ず大判で確認 小さなカタログに載っている色は、実際の外壁に塗ったときの印象と大きく異なることがあります。最低でもA4サイズ程度の「大判サンプル」で確認し、屋外の自然光で見ることが重要です。 ② 太陽光での見え方をチェック 時間帯や天気によって、色の印象は変わります。朝・昼・夕方と時間を変えて見比べることで、実際の見え方に近づけることができます。 ③ ツヤあり・なしの違いに注意 同じ色でも、「ツヤあり」と「ツヤなし」で雰囲気が大きく変わります。高級感を出したいならややツヤを抑えたマット系、清潔感や明るさを出したいならツヤありが向いています。 ④ 汚れが目立ちにくい色を選ぶ 白や黒は人気ですが、汚れが目立ちやすいというデメリットもあります。アイボリーやグレー、ベージュなどの中間色は比較的汚れが目立ちにくく、人気が高い傾向にあります。 ⑤ 付帯部とのバランスを考える 外壁単体で色を決めるのではなく、屋根・雨樋・サッシ・玄関ドアとのバランスを考えることも大切です。メインカラーに加えて、アクセントカラー・サブカラーをどう配置するかを全体で設計しましょう。 汚れが目立たない色4選!現場に立つプロが写真を使って徹底解説! - 柏原市、羽曳野市、藤井寺市で外壁塗装をお考えなら株式会社聖建装工業にお任せ下さい 3. 人気カラーランキング(2025年版) ここでは、2025年に人気が高まっている外壁カラーの傾向をご紹介します。 ① グレージュ(グレー+ベージュ) 落ち着きと柔らかさを兼ね備えたカラー。モダンで上品な印象に仕上がり、和洋どちらの住宅にも合います。近年特に人気が上昇中。 ② スモーキーブルー 優しい青みを含んだくすみカラー。落ち着いた印象を与え、ナチュラル志向の方に好まれています。木製のドアや黒のサッシと相性抜群です。 ③ チャコールグレー 濃いグレーで重厚感と高級感を演出。黒ほど重くならず、汚れも目立ちにくいため、都会的な印象を求める人におすすめ。 ④ アイボリーホワイト 清潔感があり、どの街並みにも合う万能カラー。経年劣化にも比較的強く、色あせしにくいのも特徴です。 ⑤ アースカラー(オリーブ、モカブラウン、テラコッタなど) 自然素材に調和する色合いで、木造住宅やナチュラルテイストの家にぴったり。外構や庭と合わせたトータルデザインに向いています。 アースカラーとはどんな色?歴史や魅力、似合う骨格・顏タイプを徹底解説! 4. 色を選ぶ際に使える便利ツール ● カラシミュレーション 多くの塗装会社や塗料メーカーでは、外壁のカラーパターンをパソコンやスマートフォンでシミュレーションできるサービスを提供しています。ご自宅の写真を使って色を重ねてみることで、より現実に近いイメージが得られます。 【豆知識】カラーシミュレーションってなんだろう?? | 木村塗装工業 ● 建築士・塗装職人のアドバイス プロの視点で、建物の形状や周囲の景観に合った色を提案してくれることもあります。最終決定前に専門家と相談するのがおすすめです。 5. 色選びの失敗例と回避法 ● 失敗例① 思ったよりも派手だった → 原因:サンプルで見た色が外で見ると明るく見えた → 対策:実際の壁に仮塗りして確認する「試し塗りサービス」を活用しましょう。 ● 失敗例② 近隣の家と同じだった → 原因:人気色を選んだら隣家と被った → 対策:地域の建物を事前に見て回り、近隣の配色を避ける工夫が必要です。 ● 失敗例③ 流行色を選んだがすぐに飽きた → 原因:個性的すぎて飽きがきた → 対策:ベースは落ち着いた色にして、アクセントカラーで遊ぶのがおすすめです。 まとめ 外壁塗装の色選びは、家の価値や印象を大きく左右する重要なポイントです。大きな費用がかかるため、慎重に、そして戦略的に選ぶことが後悔しない秘訣です。2025年は、落ち着いた「くすみカラー」や自然に調和する「アースカラー」がトレンドとなっています。色見本やシミュレーションを活用しながら、自分たちの暮らしにふさわしい一色を見つけてください。スタッフブログ


 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求