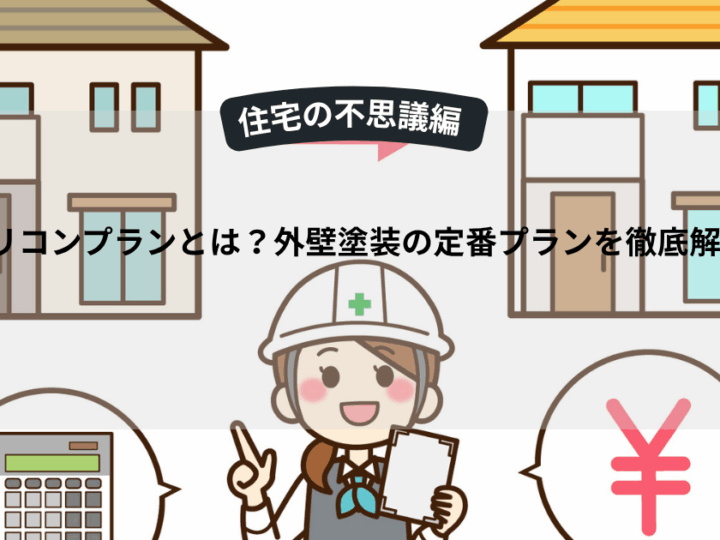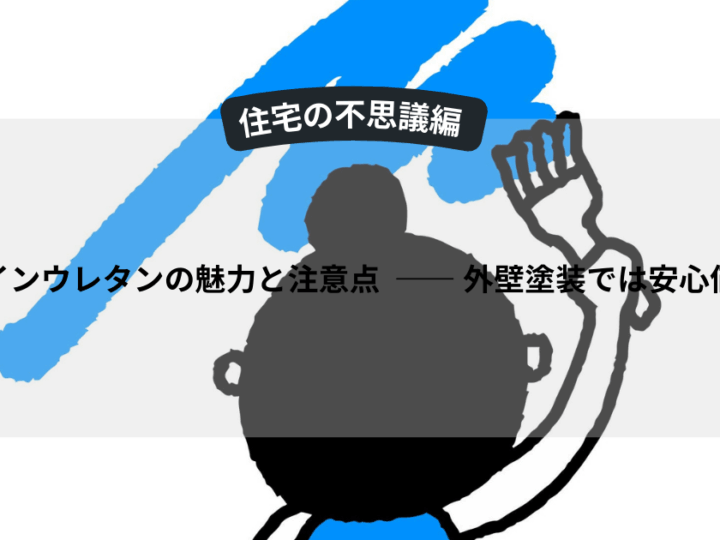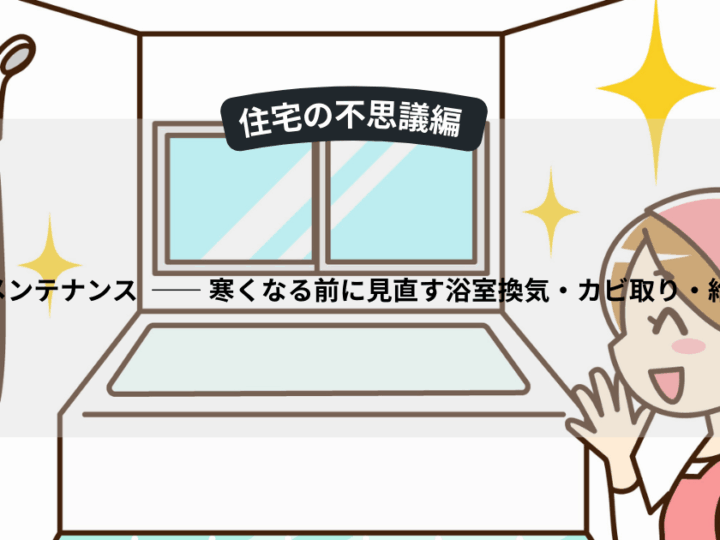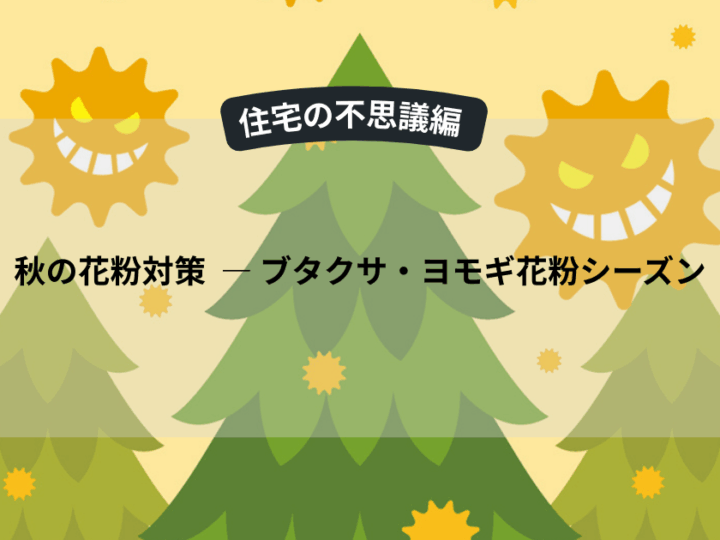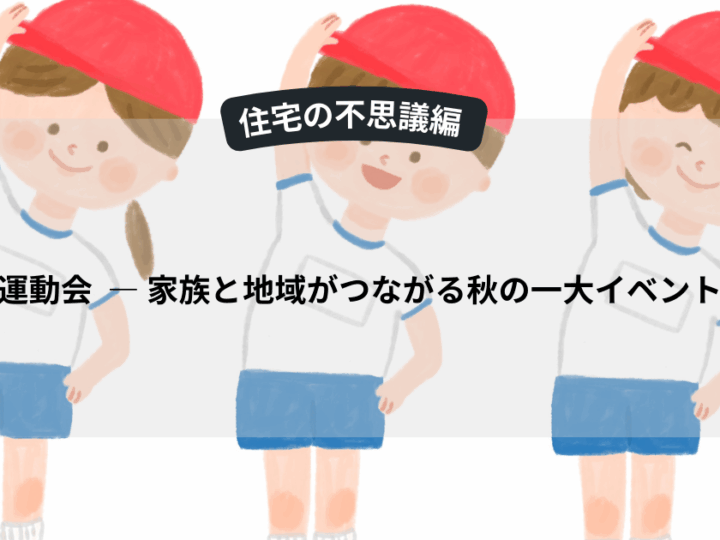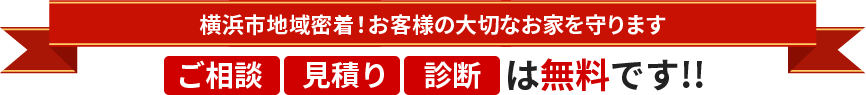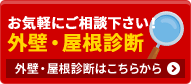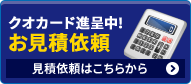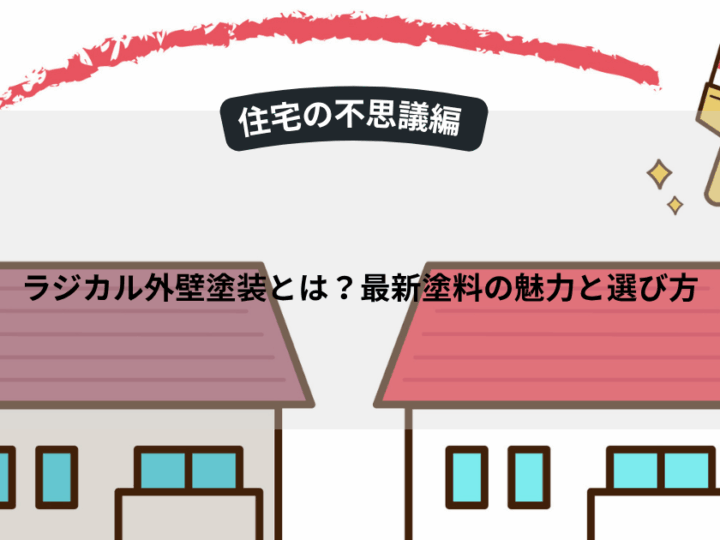
ラジカル外壁塗装とは?最新塗料の魅力と選び方
皆様こんにちは! 横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。 横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪ 外壁塗装を検討する際に、「シリコン塗料」「フッ素塗料」と並んで近年よく耳にするようになったのが 「ラジカル塗料」 です。 外壁リフォームの業界で比較的新しいジャンルに属し、「次世代の標準塗料」とも呼ばれています。実際にどんな性能があり、どんな人におすすめなのかを詳しく見ていきましょう。 1. ラジカル塗料の基本 「ラジカル」とは化学用語で、酸素や紫外線の影響によって発生する劣化因子(ラジカル分子)のことを指します。外壁塗装が劣化する最大の原因は、このラジカルによる塗膜の分解です。 ラジカル塗料は、ラジカルの発生を抑える「ラジカル制御型酸化チタン」や、安定性を高める「光安定剤」を配合した塗料 で、外壁の劣化スピードを遅らせる効果があります。 つまり、従来のシリコン塗料よりも 耐候性・耐久性に優れ、コストも比較的抑えられる のが大きな特長です。 前回の2つに、比べるとコストがあがりますが魅力的な性能が増えますよね! ラジカル塗料って何?シリコン塗料との比較やおすすめ商品ランキングを紹介!│ヌリカエ 2. ラジカル塗料のメリット (1) 耐久性が高い シリコン塗料の耐用年数が約10〜15年に対し、ラジカル塗料は 12〜16年程度 と、やや長持ちします。紫外線の強い地域や、海風・排気ガスにさらされる環境でも耐候性が高く評価されています。 (2) コストパフォーマンスが良い フッ素や無機塗料と比べると価格は抑えめ。それでいて耐久性はシリコン以上。つまり「価格と性能のちょうど中間」に位置するのがラジカル塗料です。 (3) 防汚性・美観保持に優れる 汚れが付着しにくく、色あせやチョーキング現象(外壁を触ると白い粉がつく劣化症状)を抑制します。長期間、外壁をきれいに保てる点も魅力です。 (4) 汎用性が高い モルタル・サイディング・ALCパネルなど、多くの外壁材に対応できます。住宅地から商業施設まで幅広く使われています。 横浜ペイントでは、ちょうど真ん中のプランですね! ラジカル塗料とは?耐用年数・価格を掲載!メーカー別のおすすめ比較も解説 | 外壁塗装のあれこれ 3. ラジカル塗料のデメリット (1) 歴史が浅い ラジカル塗料が登場したのは2010年代半ばと比較的新しく、シリコンやフッ素ほどの長期的な実績がまだ十分に蓄積されていません。「20年以上持つ」といったデータは今後の検証が必要です。 (2) 商品ごとの性能差 各メーカーが独自の技術を使っているため、同じ「ラジカル塗料」でも性能差が出やすいのが現状です。見積書で「ラジカル塗料」と記載されていても、必ず メーカー名と商品名を確認することが重要 です。 (3) フッ素・無機ほどの耐久性はない シリコンよりは強いものの、フッ素や無機塗料には劣ります。「30年安心して塗り替え不要にしたい」と考える方には物足りない可能性があります。 比較的新しいので、長期的な実績がないのでもしかしたら20年以上持つ可能性もあるかもしれませんね! ラジカル塗料について徹底解説!特徴と長所・短所についてのまとめ | 石川商店 4. 他の塗料との比較 シリコン塗料 vs ラジカル塗料 シリコン:10〜15年持つ。標準的で価格も安定。 ラジカル:12〜16年持つ。シリコンより高性能でコスパ良し。 →「シリコンの一歩上を狙いたい人」におすすめ。 フッ素塗料 vs ラジカル塗料 フッ素:15〜20年持つ。高額。 ラジカル:12〜16年持つ。価格はフッ素の7割程度。 →「長く持たせたいが、費用はできるだけ抑えたい人」にラジカルは魅力的。 5. ラジカル塗料の施工事例 ある築15年の住宅で、ラジカル塗料を採用したケースを紹介します。 外壁:サイディングボード 塗装費用:約110万円(30坪2階建て) 使用塗料:日本ペイント「パーフェクトトップ」 仕上がり:艶のある美しい外観で、雨の後も汚れが流れやすい 施工から10年後の点検では、色あせやチョーキングが少なく、再塗装まで余裕があるとのことでした。シリコン塗料と比較すると、やはり耐久性の差を感じられるとの声もあります。 6. こんな人におすすめ シリコン塗料より長持ちする塗料を探している フッ素や無機ほどの高額予算は用意できない 初めての外壁塗装で、安心感とコスパを両立したい 10〜15年ごとにきちんとメンテナンスする計画がある 7. まとめ ラジカル外壁塗装は、シリコン塗料の一歩上をいく性能を持ちながら、フッ素や無機ほど高額ではない「バランス型の塗料」です。 耐用年数:12〜16年 コスト:中価格帯(シリコンより高いがフッ素より安い) メリット:耐候性・防汚性に優れ、美観を長持ち デメリット:実績が浅い、商品差がある 「予算と耐久性のバランスを重視したい」「できるだけ長持ちさせたいけどコストも大切」という方に、まさに最適な選択肢といえるでしょう。また、商品が新しいので実績が少なくもしかしたらすごく長持ちなんてこともあるので期待できる商品かもしれません。 感想 ラジカル塗料が登場した当初は「本当にシリコン以上の耐久性があるのだろうか?」と半信半疑でした。外壁塗装業界では新しい塗料が次々と出ますが、中には期待ほど普及しないものもあるからです。 しかし、実際に施工された住宅を何年か追ってみると、色あせやチョーキングの少なさに驚かされました。シリコンに比べてワンランク上の安心感がありながら、価格が抑えられているのは確かに魅力的です。 もし自宅を10〜15年ごとにメンテナンスしていくつもりなら、ラジカル塗料は「今一番現実的な選択肢」だと感じます。逆に「一度の塗装でできるだけ長く持たせたい」場合は、やはりフッ素や無機が向いているでしょう。 結局のところ、塗料選びは 「今後何年その家に住むのか」「どれくらいの予算をかけるのか」 によって答えが変わります。ラジカル外壁塗装は、そうした多様なニーズの中で「ちょうど良い落としどころ」として、多くの方に支持される塗料だと実感しています。 2025年10月03日 更新スタッフブログ


 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求