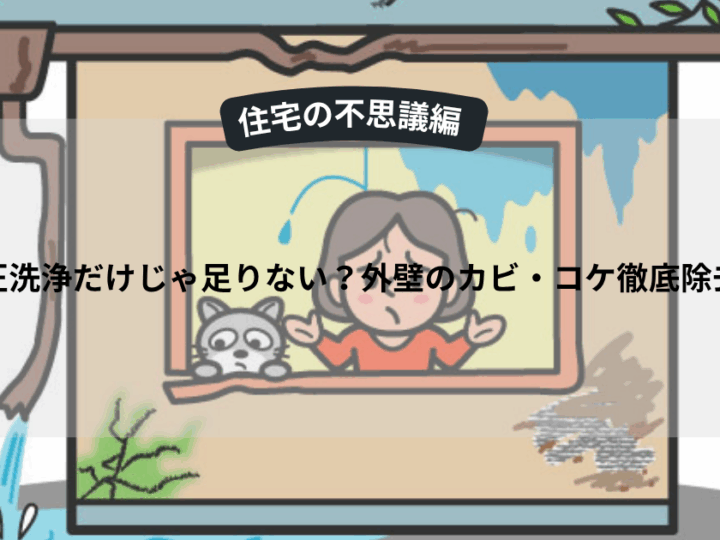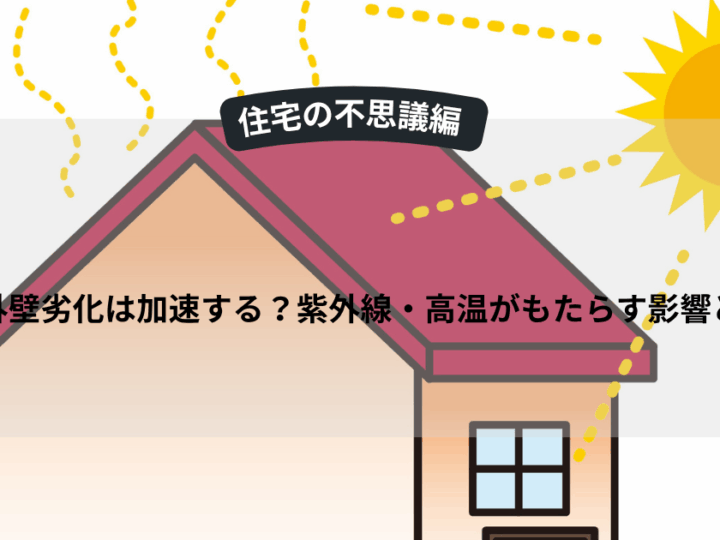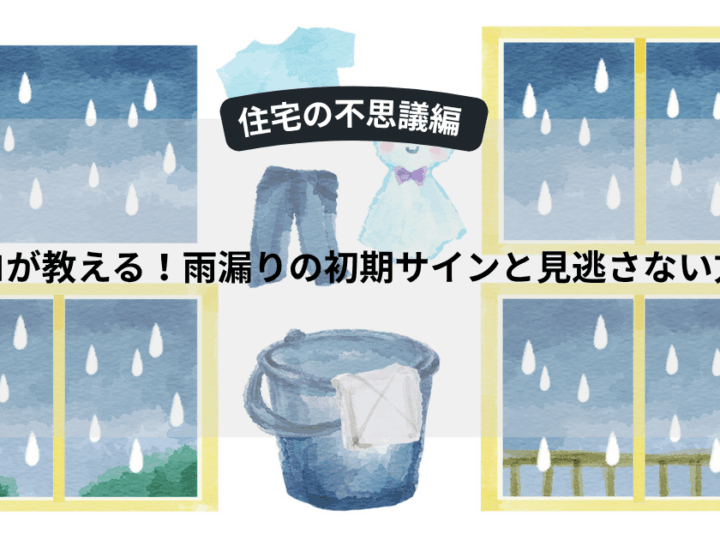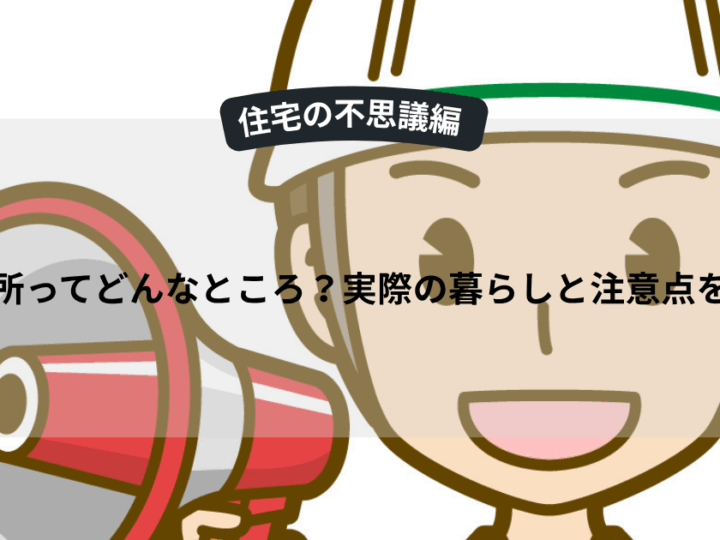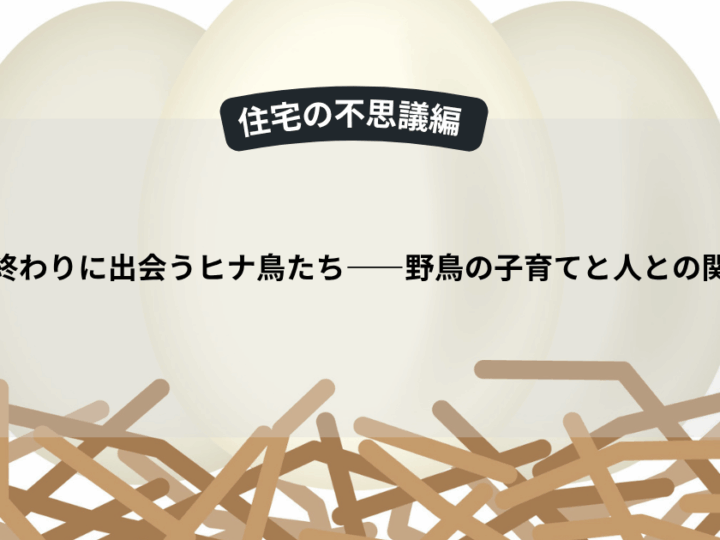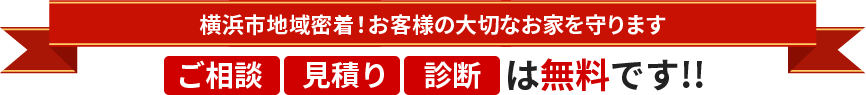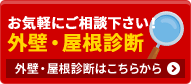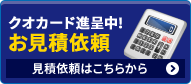夏のお盆とは?由来・意味・地域ごとの風習・現代の過ごし方
皆様こんにちは! 横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。 横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪ 今回は、お盆について由来やあれこれ説明させて頂きます。 ぜひ、最後までご覧頂ければ嬉しいです。 はじめに 1. お盆とは何か お盆は、日本で古くから行われてきた祖先の霊を迎え、供養する行事です。 一般的には毎年8月13日〜16日に行われ、夏の一大行事として全国で親しまれています。 正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、仏教行事の一つですが、日本では神道や民間信仰とも融合し、独自の風習が発展しました。 2. お盆の由来 お盆の起源は、仏教の「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」に登場する逸話にあります。 2-1. 盂蘭盆経の物語 釈迦の弟子・目連(もくれん)が、亡くなった母が餓鬼道で苦しんでいる姿を見ます。 母を救うために釈迦に相談すると、「7月15日に修行僧へ供物を捧げ、功徳を積みなさい」と教えられました。 目連がその通りに行うと母は救われ、この行為が祖先供養の行事として広まりました。 この「祖先を供養して功徳を積む」という思想が、日本に伝わったのは飛鳥時代とされます。 目連(モッガラーナ)とは?母を餓鬼道から救い、お盆の元になった神通第一の目連尊者の最期 3. 日本での広まりと変化 仏教が伝来した奈良〜平安時代、お盆は宮中や寺院で行われる儀式でした。 鎌倉〜江戸時代には庶民にも広まり、先祖の霊を家に迎えてもてなし、送り出す形が定着します。 特に農村では、夏の農作業がひと段落する時期と重なり、親族が集まりやすかったことから、お盆=家族の再会と先祖供養の期間となりました。 【保存版】お盆の意味・由来・時期と供養の基本をわかりやすく解説 4. お盆の日程 お盆には大きく分けて旧盆と**新盆(7月盆)**があります。 種類 時期 地域の例 新盆(7月盆) 7月13〜16日 東京・神奈川・静岡など 旧盆(8月盆) 8月13〜16日 全国的に多数 旧暦盆 旧暦7月15日頃 沖縄・奄美など 現在、全国的には8月13日〜16日の旧盆が主流ですが、東京などでは7月盆を続けている地域もあります。 5. お盆の流れと行事 5-1. 迎え盆(8月13日) 家の門や玄関前で迎え火を焚き、祖先の霊が迷わず帰ってこられるよう道しるべにします。 仏壇や盆棚(精霊棚)を飾り、花や果物、故人の好物を供えます。 5-2. 中日(8月14〜15日) 親族が集まり、仏前でお経をあげたり、食事を共にします。 お墓参りをして、墓石を清め、花やお供え物をします。 5-3. 送り盆(8月16日) 送り火を焚き、霊をあの世へ見送ります。 京都の「五山の送り火」が有名で、大文字焼きなどがその象徴です。 お盆のすべてが分かる!迷わない準備・やることチェックリスト - お葬式と法要の常識ガイド 6. 地域ごとの風習 6-1. 東北・北海道 墓参りのあと、お墓でおにぎりやお菓子を食べる風習あり。 精霊馬(きゅうりやなすに割り箸を刺して馬や牛に見立てたもの)を飾る。 6-2. 関東 東京は7月盆が多く、迎え火・送り火を行う家庭も。 新盆(故人が亡くなって初めて迎えるお盆)には白い提灯を飾る。 6-3. 関西 京都の「五山の送り火」や奈良の「なら燈花会」など、夜の送り行事が盛ん。 6-4. 沖縄・奄美 エイサー踊りで祖先を送る。 旧暦のお盆に合わせて行うため、毎年日程が変わる。 地域別お盆の風習:日本各地の文化を紹介!結婚したばかりで相手の地域の風習がわからない方必見です。 - 7. お盆に食べるもの 精進料理:肉や魚を使わず野菜や豆腐を中心とした料理 団子:霊を迎えるための「迎え団子」、送るための「送り団子」 そうめん:夏の食べ物として定番、また「細く長く生きる」願いも込められる 8. 現代のお盆の過ごし方 実家に帰省して墓参り 親族との食事会 旅行やレジャーと合わせる家庭も増加 都市部では迎え火・送り火を省略し、お墓参りのみ行うケースも多い 9. お盆と交通混雑 お盆期間中は、帰省や旅行で新幹線や高速道路が大混雑します。 これをお盆ラッシュと呼び、毎年ニュースになるほどです。 混雑ピークは8月13日前後と、Uターンの16日前後です。 10. まとめ お盆は、単なる夏休みイベントではなく、祖先を敬い、家族や親族の絆を深める期間です。 地域によって日程や風習は異なりますが、共通しているのは「感謝の気持ちで先祖を迎え、送り出す」という心。 忙しい現代でも、この時間を大切に過ごすことは、私たちの暮らしに深みと温かさを与えてくれます。 2025年08月11日 更新スタッフブログ


 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求