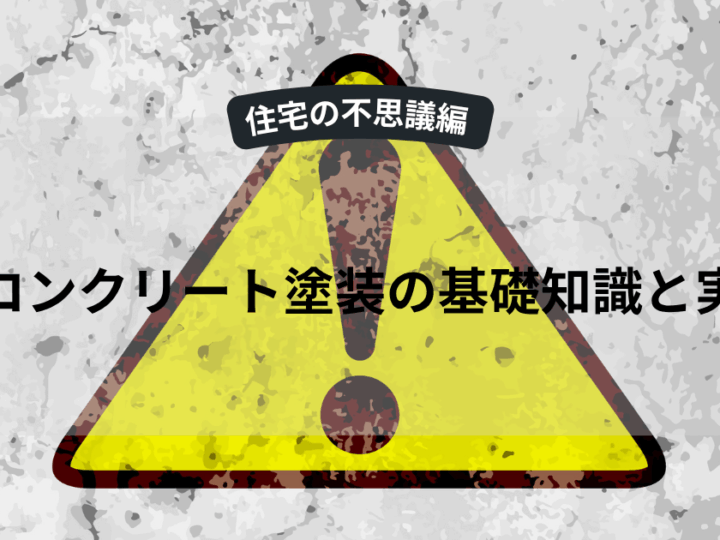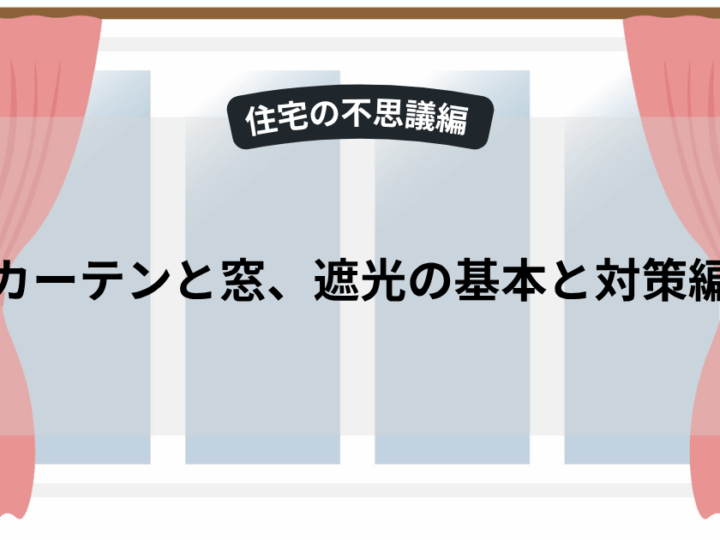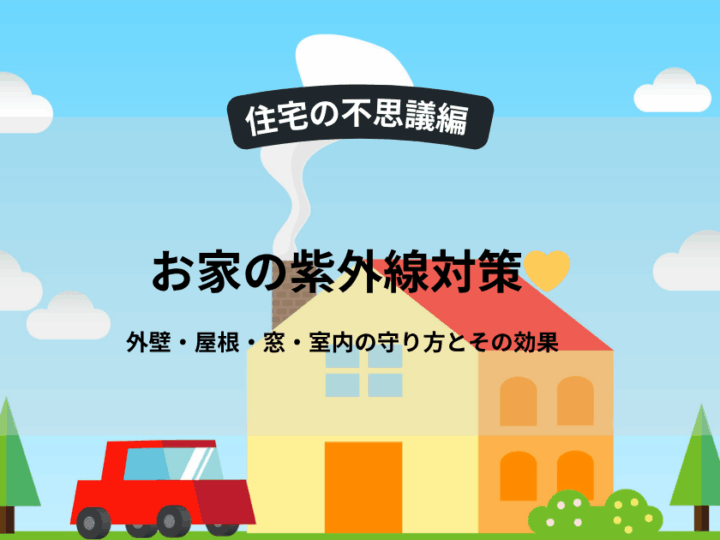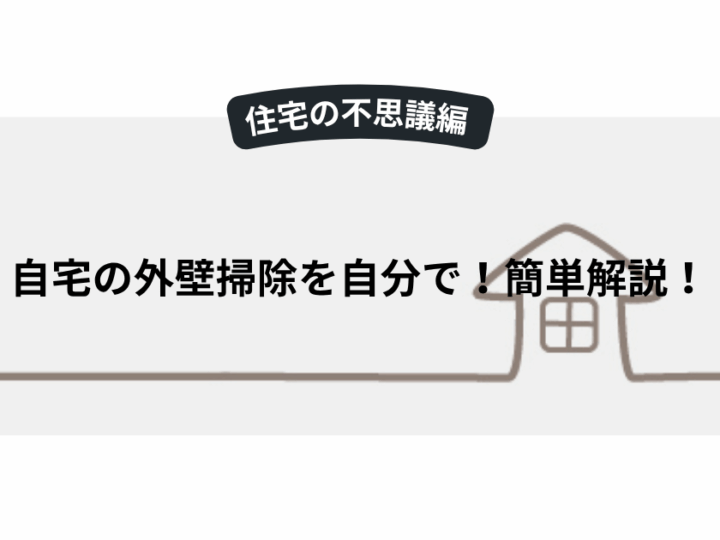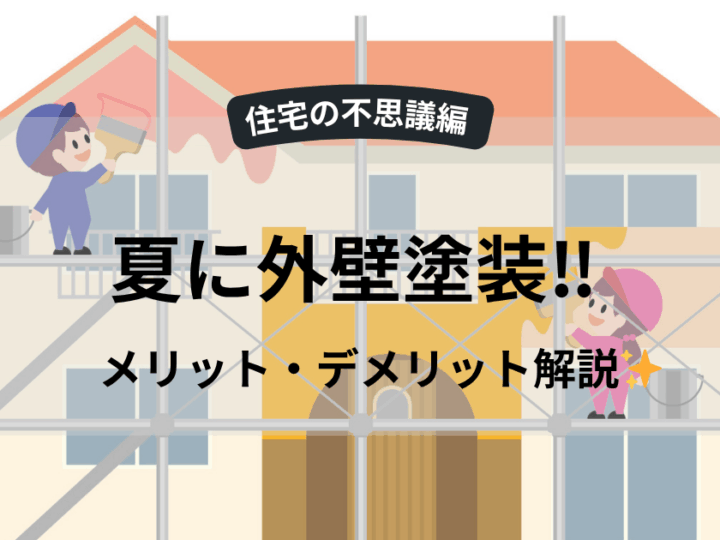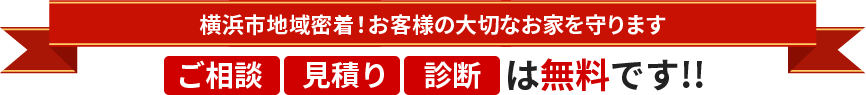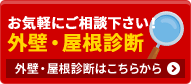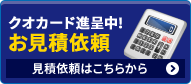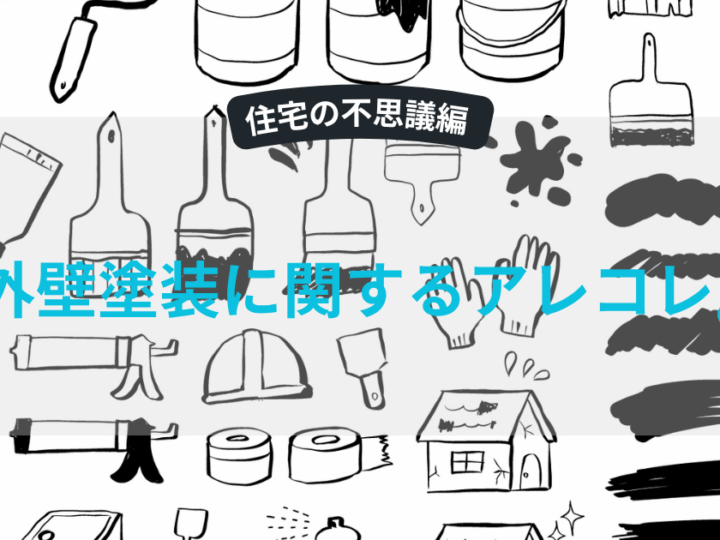
外壁塗装に関するアレコレ¿
みなさまこんにちわ! 横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。 横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪ 今回は、塗装メーカーやランキングについて解説させて頂きます。 ぜひ、最後までご覧頂ければうれしいです♪ 1. おすすめ塗料メーカー一覧(国内主要メーカー) ■ 日本ペイント(ニッペ) ・業界最大手。住宅用から工場、橋梁まで網羅。 ・代表商品:「パーフェクトトップ」「ファインシリコンフレッシュ」「ピュアライドUVプロテクトクリヤー」 ・特長:コスパ・カラーバリエーションに強い。 ■ 関西ペイント(カンペ) ・老舗大手。耐候性・高性能商品に定評。 ・代表商品:「RSシルバーグロスSi」「アレスダイナミックTOP」 ・特長:住宅塗料でも遮熱・ラジカル制御塗料が人気。 ■ エスケー化研 ・建築仕上げ材国内トップ。防水・外壁・屋根塗装に強い。 ・代表商品:「プレミアムシリコン」「クリーンマイルドシリーズ」 ・特長:ラジカル制御型塗料が特に評価高い。 ■ アステックペイント ・九州発の成長メーカー。塗料の機能性重視。 ・代表商品:「超低汚染リファインSi」「スーパーシャネツサーモ」 ・特長:高耐久・遮熱・低汚染性で評価急上昇中。 ■ SKK(スズカファイン) ・意匠系塗料に強み。外観デザイン重視住宅向け。 ・代表商品:「ベルアートSi」「セラミシリコン」 ・特長:外壁デザイン塗材の品ぞろえが豊富。 ■ 水谷ペイント ・金属系(屋根・トタン)塗料に特化。 ・代表商品:「ナノコンポジットW」「パワーシリコンマイルドⅡ」 ・特長:サイディング、鉄部向け塗料充実。 2. 最新塗料ランキング(2025年版・人気順) 順位 商品名 メーカー 特徴 耐久年数 1位 パーフェクトトップ 日本ペイント コスパ最強のシリコン 12〜15年 2位 プレミアムシリコン エスケー化研 ラジカル制御型代表作 12〜15年 3位 超低汚染リファインSi アステックペイント 超低汚染・遮熱・防藻 15年超 4位 ファインパーフェクトトップ 日本ペイント 高耐久ラジカル制御 15年超 5位 RSシルバーグロスSi 関西ペイント 高級感・艶持続 15年超 6位 スーパーシャネツサーモSi アステックペイント 遮熱・断熱に特化 15年 7位 アレスダイナミックTOP 関西ペイント ラジカル制御・低汚染 12〜15年 8位 ピュアライドUVプロテクトクリヤー 日本ペイント サイディング専用クリヤー 10〜12年 9位 ナノコンポジットW 水谷ペイント セルフクリーニング効果 10〜12年 10位 セラミシリコン スズカファイン 高耐候シリコン樹脂 10〜12年 3. 戸建住宅での人気塗料(2025年版) 【コスト重視層】 パーフェクトトップ(ニッペ) 低価格・高品質シリコンの定番。築10年〜20年住宅向け。 【耐久性重視層】 プレミアムシリコン(エスケー化研) ラジカル制御型で塗り替え周期15年。雨・紫外線に強い。 超低汚染リファインSi(アステック) 外壁の汚れが気になる立地に最適。長期的に美観保持。 【遮熱・断熱重視層(猛暑対策)】 スーパーシャネツサーモSi(アステック) 屋根・外壁両用。夏の冷房費削減実績多数。 【デザイン・美観重視層】 ピュアライドUVプロテクトクリヤー(ニッペ) サイディング柄活かし+UV防御。築浅住宅の人気品。 ベルアートSi(スズカファイン) 吹付け・意匠仕上げ専用。オリジナリティ外壁向き。 まとめ 迷ったら「パーフェクトトップ」or「プレミアムシリコン」がおすすめ → コスパ、耐久性、施工性の3拍子揃い。 遮熱希望なら「スーパーシャネツサーモ」シリーズ → 屋根・壁トータルで断熱。 汚れ対策なら「超低汚染リファイン」シリーズ → 都市部や車通りの多い地域向き。 ♦新築・築浅住宅向けおすすめ塗料(築5~10年未満) ■ クリヤー塗料(透明仕上げ) 新築・築浅の「窯業系サイディング」「タイル調サイディング」に最適。 デザインを活かしつつ外壁保護。 商品名 メーカー 特徴 耐用年数 ピュアライドUVプロテクトクリヤー 日本ペイント サイディング専用UVカット 10~12年 クリーンSDトップ エスケー化研 超低汚染タイプ、艶あり・艶消し選択可 12年程度 セラミクリヤー スズカファイン 高耐候性・防汚性に優れる 10~12年 ■ ラジカル制御型塗料 築浅で「色変え」「長期メンテナンスフリー」を求める場合におすすめ。 商品名 メーカー 特徴 耐用年数 ファインパーフェクトトップ 日本ペイント ラジカル制御の定番 15年超 プレミアムシリコン エスケー化研 コスパ良し・カラーバリエ豊富 12~15年 アレスダイナミックTOP 関西ペイント UV耐性・防汚性◎ 12~15年 ■ 遮熱塗料(断熱対策) 新築住宅の省エネ性能UP・冷房効率向上目的。 商品名 メーカー 特徴 耐用年数 スーパーシャネツサーモSi アステックペイント 遮熱・防汚・高耐久 15年 サーモアイSi 日本ペイント 赤外線反射率最高クラス 10~15年 2. フッ素・無機塗料トップ10(2025年版) 「超高耐久」「長期メンテナンスフリー」を求める方向け。 フッ素系・無機系は20年以上の耐候性を誇る塗料も多い。 順位 商品名 メーカー タイプ 特徴 耐用年数 1位 ルミステージ AGC フッ素 最高級、30年クラス 20~30年 2位 ファイン4Fセラミック 日本ペイント フッ素 コスト・耐久性バランス◎ 15~20年 3位 セラミシリコンフッ素 スズカファイン フッ素 美観・防藻・防カビ 15~20年 4位 プレミアム無機 アステックペイント 無機 超低汚染・高耐久 20~25年 5位 スーパーセラタイトF エスケー化研 フッ素 超親水性セルフクリーニング 15~20年 6位 ナノコンポジットF 水谷ペイント フッ素 防汚・光沢保持 15~20年 7位 無機ハイブリッドコート アステックペイント 無機 防水+フッ素樹脂のハイブリッド 20年 8位 クリーンマイルドフッソ エスケー化研 フッ素 コストパフォーマンス良 15~18年 9位 ピュアアクリル無機 アステックペイント 無機 伸縮・ひび割れ防止性能 20年 10位 超低汚染リファインMF アステックペイント フッ素・無機混合 低汚染・高耐候性 20~25年 まとめ ●新築・築浅なら デザイン保持重視 →「UVプロテクトクリヤー」「クリーンSDトップ」 高耐久カラー重視 →「プレミアムシリコン」「ファインパーフェクトトップ」 断熱遮熱重視 →「スーパーシャネツサーモSi」「サーモアイSi」 ●フッ素・無機なら 最長寿命 →「ルミステージ(AGC)」30年レベル 価格と耐久バランス →「ファイン4Fセラミック」 セルフクリーニング+美観維持 →「スーパーセラタイトF」 ご自身の住宅にあったものを選ぶというのはとても大変なことですね! そんな時はぜひ、横浜ペイントにご相談ください!!!じっくりご相談に乗らせて頂きます♪ 2025年06月26日 更新スタッフブログ


 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求