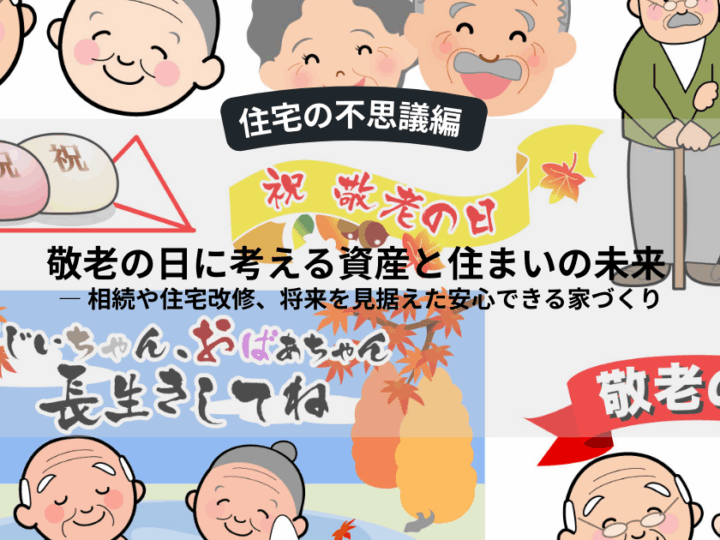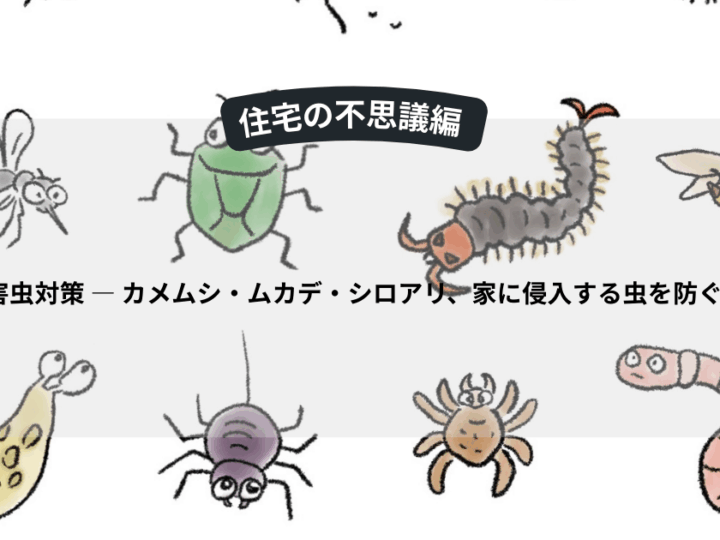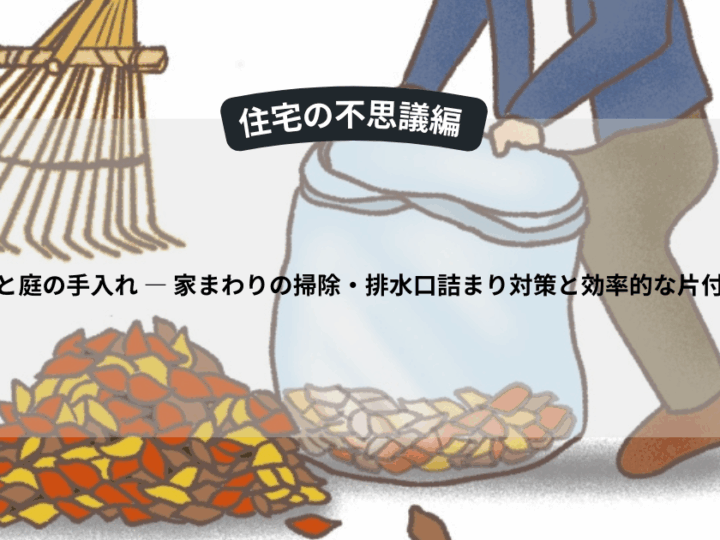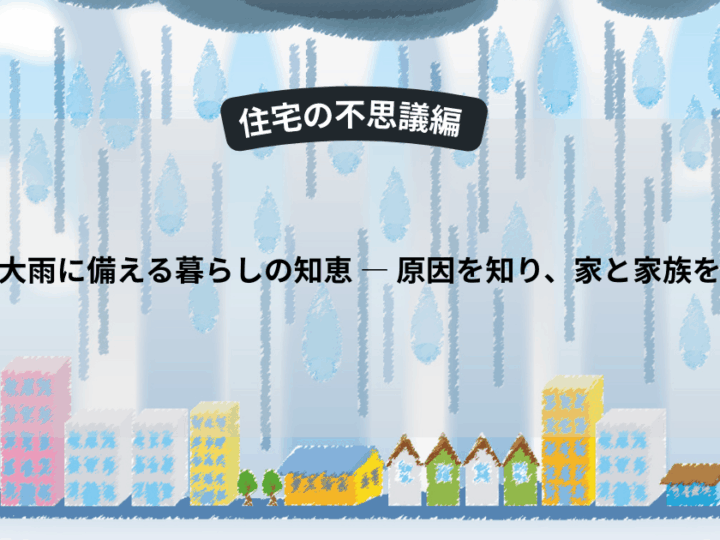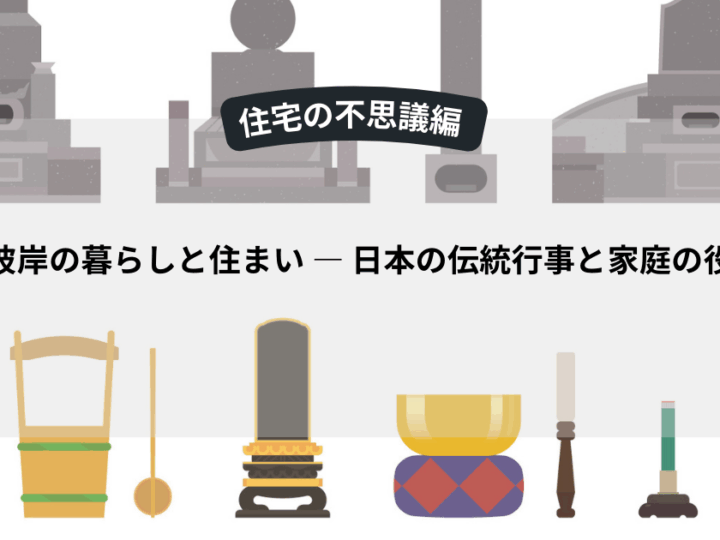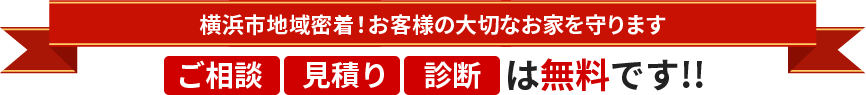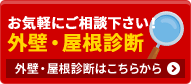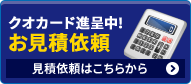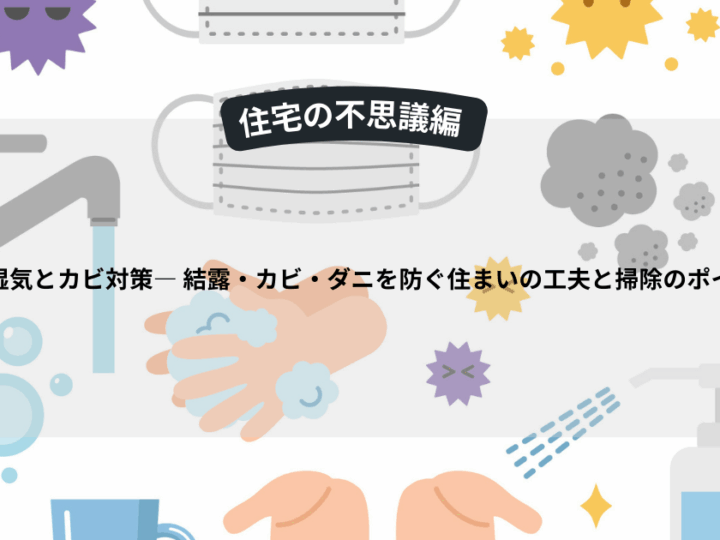
秋の湿気とカビ対策― 結露・カビ・ダニを防ぐ住まいの工夫と掃除のポイント
皆様こんにちは! 横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。 横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪ 秋は過ごしやすい季節ですが、昼夜の寒暖差が大きくなり、湿気が家の中にこもりやすい時期でもあります。 特に日本では秋雨前線の影響で雨が続き、気づかないうちに家の中がしっとりと湿ってしまうことも少なくありません。 この時期に放置された湿気は、カビやダニの発生源となり、アレルギーや体調不良を引き起こす可能性があります。そこで今回は、秋の湿気とカビ対策について、具体的な住まいの工夫や掃除のポイントを解説します。 1. 秋に湿気がたまりやすい理由 秋は気温が下がり、室内外の温度差が大きくなるため、結露が発生しやすくなります。特に朝晩冷え込むと窓ガラスやサッシに水滴が付き、その水分が壁やカーテンに吸収されることで、カビの温床になります。また、夏にフル稼働していたエアコンを使わなくなることで換気が減り、空気の循環が滞りやすい点も湿気がこもる原因のひとつです。さらに、秋は洗濯物を室内干しする機会も増え、部屋干し臭やカビの発生リスクが高まります。のどが痛くなったり体調不調になることも少なくないですね、、、 2. 結露を防ぐための工夫 (1)換気を意識する 窓を開ける時間を1日2〜3回、10分程度確保するだけでも湿気は減らせます。対角線上に窓を開けて空気を流す「クロス換気」が効果的です。特に朝起きた直後と夜寝る前の換気はおすすめです。雨の日でも、少し窓を開けて換気するだけで湿気がこもるのを防げます。 (2)断熱と窓対策 二重窓や内窓の設置、断熱シートの貼付けで窓の表面温度を下げにくくし、結露を防ぎます。既存の窓に貼るだけの簡易断熱フィルムもホームセンターで手に入るので、賃貸住宅でも取り入れやすい方法です。サッシの隙間風を防ぐテープや、結露吸水テープを貼るのも有効です。 (3)除湿機やサーキュレーターの活用 湿度が高いと感じたら除湿機を稼働させ、60%以下に保つことが理想です。部屋の空気を循環させることで、湿気が偏らず結露も減少します。除湿機は洗濯物の部屋干しにも活用でき、臭い対策にもなります。 私は、換気を心がけても一日一回換気できるかできないかで本当に反省しないといけませんね、、、 それと、除湿器などは昔活用してましたが、お掃除ができず数年でダメにしてしまった記憶があります。 結露を防ぐためにも断熱性能の良い家に住むことは一番大切かもしれませんね♪ 除湿機とサーキュレーターを上手に併用する方法は?置き方を工夫した湿度対策から注意点まで徹底解説 - オーディンウィズダム 3. カビを防ぐ掃除とメンテナンス (1)窓枠・サッシの掃除 結露で水分がたまりやすい窓枠は、こまめに拭き取りましょう。黒ずみが出てきたら中性洗剤で掃除し、アルコールスプレーで仕上げると再発防止になります。木枠の場合は水分がしみこまないよう、乾いた布で拭くことが大切です。 (2)浴室と洗面所の換気 湿度が最も高い場所である浴室は、入浴後すぐに換気扇を回し、壁や床をスクイージーで水切りしておくとカビの繁殖を抑えられます。洗面所の床マットも湿ったまま放置せず、こまめに洗濯して乾かしましょう。さらに排水口の掃除も定期的に行い、カビやぬめりを防ぎます。 (3)家具の配置を見直す 壁際に家具をぴったりつけると空気が滞留して湿気がたまりやすくなります。数センチ空けることで通気性が向上し、壁にカビが生えるリスクを減らせます。押入れやクローゼットの中にはすのこや除湿剤を置くとより効果的です。 いつも掃除しないところを掃除しないといけませんね。わかっていてもなかなか掃除が行き届いていませんよね。 https://kokokara-sisanunyo.com/bathroom-exhaust-fan-necessary/ 4. ダニ対策も同時に行う 湿気はダニの繁殖条件でもあります。秋はダニの死骸やフンが増え、ハウスダストアレルギーの原因になりやすい時期です。 寝具は週1回天日干し、または乾燥機にかける 布団やマットレスに掃除機をかける(専用ノズルがあればさらに効果的) カーペットやラグは丸洗いできるものを選ぶ 湿度管理を徹底する(50〜60%をキープ) ぬいぐるみやクッションも定期的に洗濯してダニを減らす これらの対策でダニやアレルゲンを大幅に減らすことができます。天気干しはとっても大切ですね。夏と違い曇りの日やあまり太陽が出ていない日が続くようなら乾燥機も大切ですね! 寝具の手入れ、どれくらいの頻度が正解?布団・マットレスのお手入れガイド | 志なのや 5. プロに依頼する選択肢 自分で掃除してもカビ臭が取れない場合や、押入れ・壁の裏側など目に見えない部分のカビが気になる場合は、ハウスクリーニング業者やリフォーム業者に相談するのも一つの方法です。防カビコーティングや調湿建材への交換など、根本的な改善が可能です。最近では調湿効果のある漆喰や珪藻土の壁材も人気で、自然素材で快適な湿度を保てる住まいづくりが注目されています。 まとめ 秋は「湿気残り」によるカビ・ダニトラブルが増える季節です。結露防止、換気、湿度管理、こまめな掃除が基本。さらに家具配置や断熱対策を工夫すれば、快適で清潔な住まいを維持できます。少しの手間をかけることで、冬本番になってからの大掃除がぐっと楽になるというメリットもあります。一番はあまりものを置かないことかもしれませんね! 感想 私自身、秋になると窓の結露や押入れのカビに悩まされていて結露でカーテンがカビだらけなんてこともありました。 家小さな工夫の積み重ねが、家の健康だけでなく家族の健康にも直結することを実感しています。 しっかり掃除しておさらばカビしたいです!今年の秋は、ぜひ読者の皆さんも“湿気対策”を暮らしの習慣に取り入れてみてください。 寒さが本格化する前に環境を整えておけば、冬をより快適に過ごせるはずです。 2025年09月16日 更新スタッフブログ


 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求