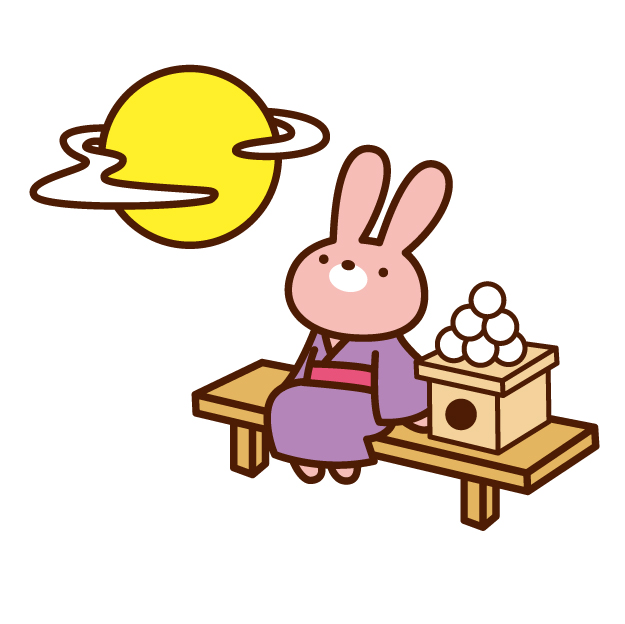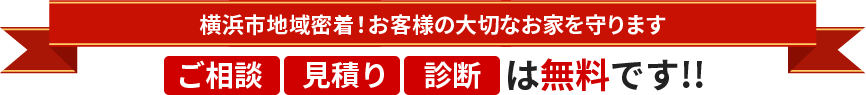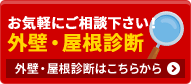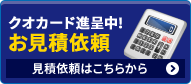お月見と日本の秋の風習 ― 伝統行事を暮らしに取り入れる
皆様こんにちは!
横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。
横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪
秋になると空気が澄み、夜空に浮かぶ月がひときわ美しく感じられます。近年は、九月も夏のような暑さが続きまったく秋をかんじられませんけれども、ハンバーガー屋さんでは月見が出たりと九月といえば、秋という印象はありますよね。
日本人にとって「お月見」は、古くから秋の風物詩として親しまれてきました。
月を眺めながら、収穫に感謝し、季節の移ろいを楽しむ――そんな時間は、忙しい現代人にとっても心を整えるひとときになるはずです。本記事では、お月見の由来や日本の秋の風習を解説し、さらに現代の暮らしにどう取り入れられるかを考えていきます。
お月見の由来
お月見の風習は、奈良時代に中国から伝わった「中秋節」が起源といわれています。当時の貴族たちは、月を眺めながら詩を詠み、宴を開き、音楽を楽しんでいました。その文化が日本に伝わり、平安時代には貴族たちの優雅な行事として定着しました。
やがて庶民の間にも広がり、農村では「十五夜」に収穫への感謝をこめて月を拝むようになりました。月を神聖視し、稲の実りや里芋の豊作を祈る行事へと変化していったのです。こうして、お月見は「自然に感謝し、恵みを分かち合う」日本らしい文化として根付いていきました。
正直、仕事や日常に追われて「今日は月見だ」と気付かない年もありますが、ふと夜空を見上げて澄んだ月が輝いているのを見つけると、なぜか心が落ち着きます。昔の人々が月に祈りを捧げた気持ちが少しわかる気がするのです。
中秋節とは?由来や風習、食べ物、日本の十五夜との違いを紹介|HANKYU FOOD おいしい読み物|フード(食品・スイーツ)|阪急百貨店公式通販 HANKYU FOOD
十五夜と十三夜
お月見といえば「十五夜」が有名ですが、実はもうひとつ大切な日があります。
-
十五夜(中秋の名月)
旧暦の8月15日にあたり、もっとも月が美しいとされる夜です。2025年は9月6日が十五夜にあたります。 -
十三夜
旧暦の9月13日にあたり、日本独自の風習です。十五夜の月を見たら、必ず十三夜の月も見るのが礼儀とされ、「片見月は縁起が悪い」と言われています。
十五夜が中国由来なのに対し、十三夜は日本で生まれた文化です。十五夜が里芋や稲の収穫を祝うのに対し、十三夜は栗や豆などの収穫に感謝する行事でした。このように、お月見は「一度きりの行事」ではなく、秋の実りを祝う二部構成の行事だったのです。
十三夜の意味や由来は? 十五夜との違い、2024年がいつなのかも紹介 | Oggi.jp
お月見の食べ物と飾り
お月見に欠かせないのが「月見団子」と「すすき」です。
-
月見団子
丸い団子は月を象徴し、豊作や幸福の祈りを込めて供えられます。地域によっては、芋を供える「芋名月」と呼ばれることもあります。 -
すすき
稲穂に似ていることから、五穀豊穣の象徴とされました。また、鋭い葉が魔除けの力を持つと考えられ、厄除けの意味も込められています。
このほか、里芋、栗、豆など、その季節に収穫できる作物も供えられます。供え物は翌日食べると「月の力を授かれる」と信じられており、感謝の気持ちを込めて皆で分け合うのが習わしでした。
昔は、お団子だったりが主流ですが私は、「月見バーガー」を楽しみにしてしまいます!
お月見団子の意味は?誰に供えるの?供えたあと食べていい? | 年中行事を深掘り!日本の暦
日本の秋の風習と暮らしの知恵
秋は稲刈りや収穫の季節でもあり、日本各地には多くの行事が残されています。
-
秋祭り
収穫を祝う祭りが全国で行われ、山車や神輿が町を練り歩きます。地域ごとの伝統芸能や食文化も楽しめる大切な行事です。 -
彼岸(お彼岸)
秋分の日を中心に、先祖供養を行う風習です。自然の移ろいを感じながら「命のつながり」に思いを馳せる時間でもあります。 -
紅葉狩り
山々が赤や黄色に染まる景色を愛でる風習です。古来より和歌や絵画に詠まれ、芸術文化を育む源にもなりました。
こうした秋の風習は、単に「季節を楽しむ」だけでなく、自然と人との関わりを深める役割を果たしてきました。
私の家の近くでも、秋のお祭りは開催されています!最後のお祭りという感じで夏が終わる感じで少し寂しい気持ちになりますね、、、
「お彼岸」とは? 2025年はいつ? 意味・由来やお盆との違い、ぼたもちのレシピ、過ごし方まで解説! | HugKum(はぐくむ)
現代のお月見の楽しみ方
昔ながらの行事も、少し工夫すれば現代の暮らしに取り入れやすくなります。
-
自宅で気軽に月見団子を作る
白玉粉で団子を作り、きな粉やあんこを添えるだけで立派なお月見料理に。お子さんと一緒に作れば、良い思い出になります。 -
ベランダや庭で月を眺める
お酒やお茶を片手に、ゆったりと夜空を見上げるだけでも十分に風情を味わえます。 -
季節の草花を飾る
すすきや秋の草花を花瓶に生けるだけで、室内に秋の空気が広がります。 -
地域の秋祭りに参加する
地元の伝統行事に触れることで、地域とのつながりも深まります。
現代社会では忙しさに追われ、自然や季節を意識する機会が減っていますが、こうした小さな工夫を通して「秋を感じる時間」を持つことが大切です。
まとめ
お月見は単なる「月を見る行事」ではなく、自然への感謝、収穫への祈り、そして人と人とのつながりを感じるための風習でした。十五夜と十三夜、供え物やすすきなど、ひとつひとつの意味を知ると、より深く楽しむことができます。
近年は都市部でも空気が澄む秋の夜なら意外と月がきれいに見えるものです。スマホやテレビを消して、ほんの数分でも静かに月を眺める時間を持つと、慌ただしい生活の中で「自然と共に生きている」という実感を取り戻せるように感じます。今年も月見団子を作って、家族と一緒に秋の夜長を楽しみたいと思います。
秋の風習を現代の暮らしに取り入れることは、心のゆとりを生み出し、家族や地域の絆を育むきっかけにもなります。今年の秋は、ぜひ夜空を見上げ、月の美しさと伝統文化に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。


 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求